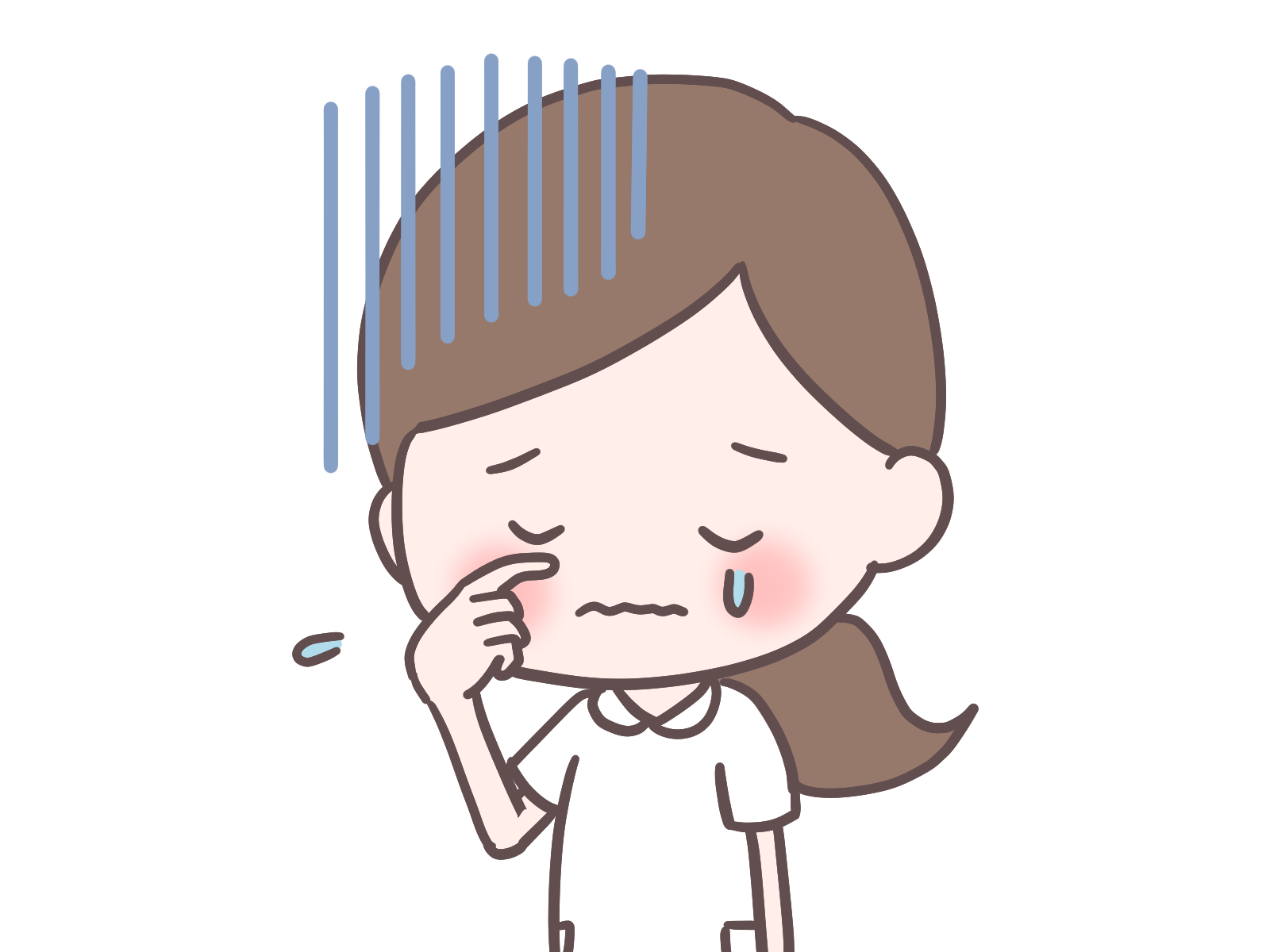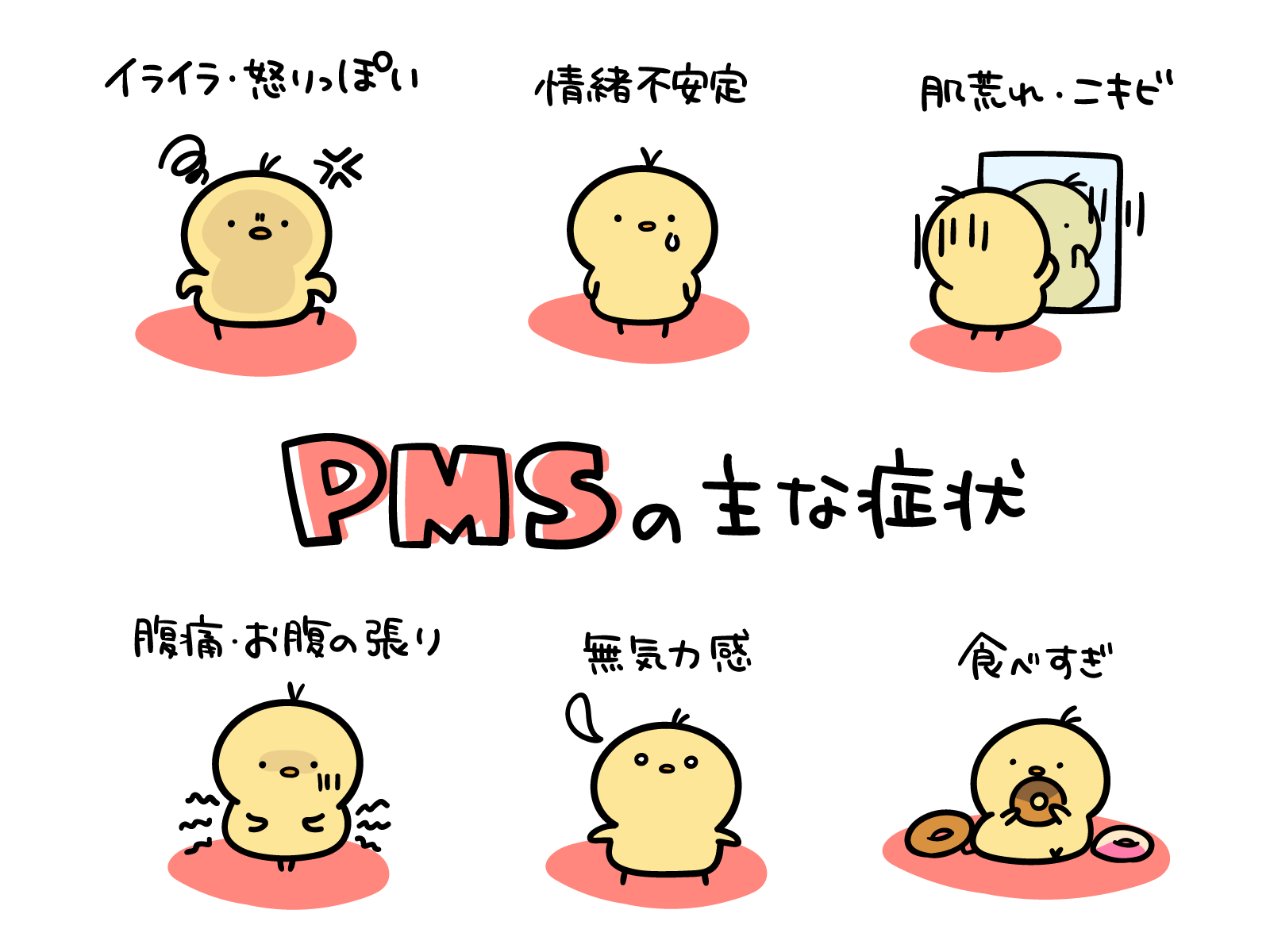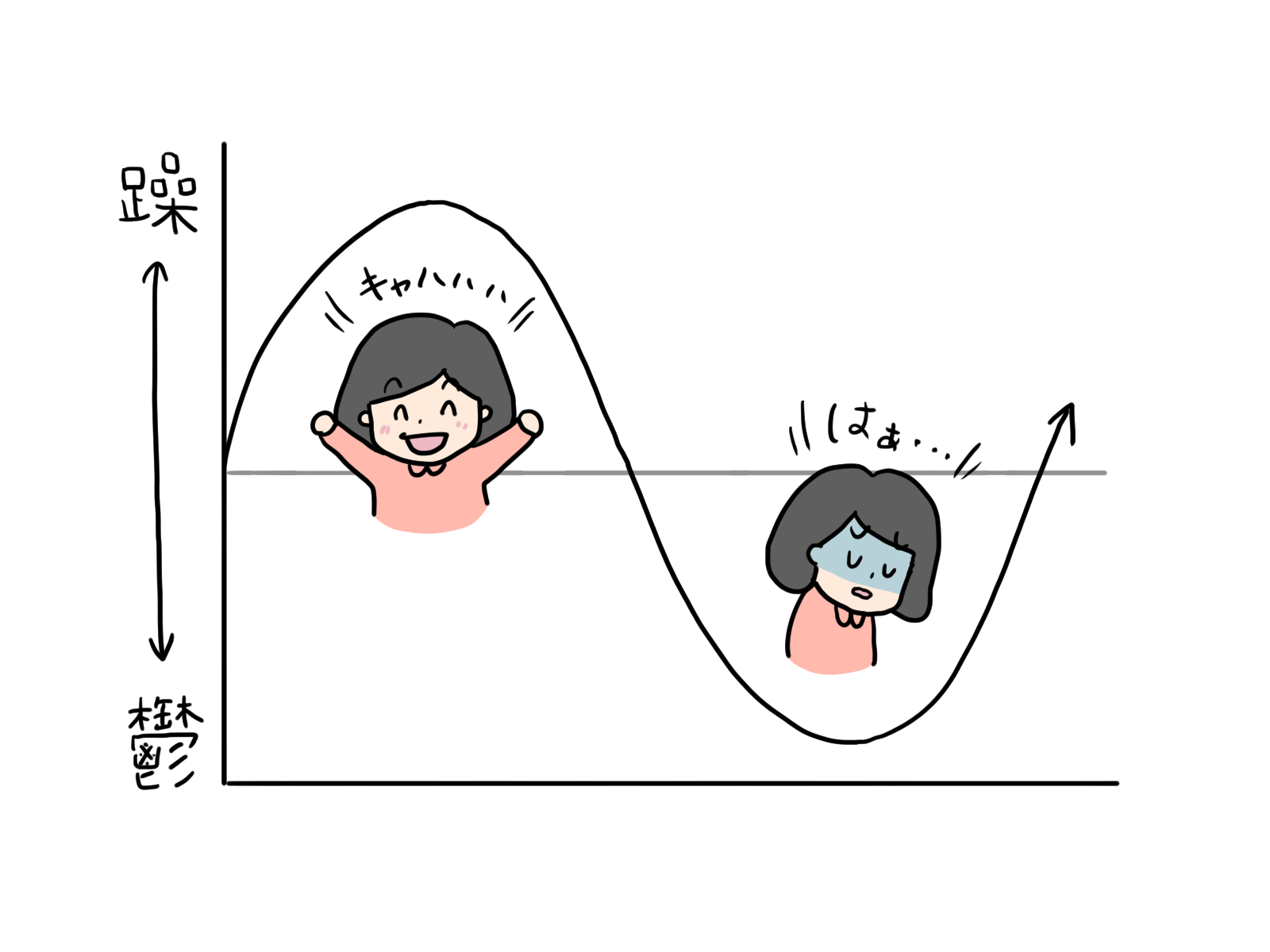ADHD(注意欠如多動症)でお悩みの方へ:特性を理解し、自分らしく生きる

「集中力が続かない…」「落ち着きがない…」「順番を待てない…」もしあなたのお子さまが、あるいはご自身がこのような特性のために、日常生活や学校生活で困難を抱えているとしたら、それはADHD(注意欠如多動症)かもしれません。
このような困難は、育て方やしつけによるものでも、子どもの努力が足りないわけでもありません。神経発達症群(発達障害)の一つであるADHDが背景にあることも多いのです。
ADHDは脳の機能の偏りによる特性ですが、適切な理解と支援を受けることで、日常生活での困りごとを減らし、自分らしく社会で活躍することが可能になります。
このページでは、ADHDの特性や症状、原因、そしてADHDのあるお子さまへの接し方などについてご紹介します。
ADHD(注意欠如多動症)とは?:脳の特性による発達障害
ADHD(Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder:注意欠如・多動症)は、不注意、多動性、衝動性の3つの症状を主な特徴とする生まれつきの精神疾患で、神経発達症群の一つとされています。海外の学術論文では18歳以下で約5%存在すると報告されています。
ADHDは、これらの3つの特徴が通常の発達の水準からすると不相応で、普段の生活に直接悪影響を及ぼすほど深刻な場合に、一定の基準をもって診断されます。
これら3つの特徴は、同時に全て現れるわけではありません。「不注意」が目立つ場合、「多動性」や「衝動性」が目立つ場合、また全てを併せ持つ場合など、子どもによって様々な形で現れます。一方、成長とともに状態が変化することもあり、例えば大人になってその特徴が自然と目立たなくなることがあります。また、本人が状況に対処する「コツ」のようなものを身につけることで、その特徴が目立たなくなることもありますが、特性そのものが全てなくなるわけではありません。
神経発達症群(発達障害)とは
神経発達症群(発達障害)とは、特定の能力や一連の情報の獲得、維持、適用に発達上の偏りがあることで、生活に悪影響が生じる神経学的な状態をいいます。ADHDのほかに、限局性学習症、自閉スペクトラム症などがあります。
ADHD(注意欠如多動症)の主な症状:不注意、多動性・衝動性
ADHDの症状は、大きく「不注意」と「多動性・衝動性」に関連する事象に分けられます。これらは年齢に相応しくない行動として、少なくとも半年以上にわたって続き、日常生活に悪影響を及ぼすことがあります。
不注意に関連する事象
- 忘れ物やなくし物が多い。
- 話しかけても聞いていないように見える。
- 約束などを忘れてしまうことがたびたびある。
- すぐに気が散ってしまう。
- 細かいことを見過ごしてしまう(ケアレスミスが多い)。
- 課題や遊びなどを途中でやめてしまう。
- 物事をやり遂げることができない。
- 順序立てることや整理整頓ができない。
- コツコツやること(勉強など)を避けたり、いやいや行う。
多動性・衝動性に関連する事象
- 手足をそわそわと動かしている。
- 授業中に席を離れてしまう。
- じっとしていられない、またはまるでエンジンで動かされるように行動する。
- 静かにできない(静かに遊んだり余暇活動につくことが難しい)。
- 急に走り出す(不適切な状況で走り回ったり高いところへ登ることがたびたびある)。
- おしゃべりが過ぎる(しゃべりすぎることがたびたびある)。
- 質問が終わる前に答えてしまう。
- 順番を抜かしてしまう(順番を待つことが難しい)。
- 友だちのしていることをさえぎる(他人を妨害し、邪魔することがたびたびある)。
現れる特性や困りごとは年齢や環境によっても異なるので、サポートもお子さま一人ひとりに合わせておこなうことが大切です。
ADHD(注意欠如多動症)の原因:脳の機能的偏り
ADHDの原因は、はっきりとはわかっていません。しかし、様々な研究より、ADHDは「脳」の機能に原因があることで、注意や行動をコントロールすることが難しくなっていると考えられています。
生まれつきのものであり、きちんとしたしつけを受けていないことや、また、逆に厳しすぎる養育環境によってADHDになるというわけではありません。
ADHDの特性を有する要因として遺伝や環境の影響を指摘する研究もありますが、まだはっきりとしたことは分かっていません。元々の素因と過去の環境、現在の環境の影響の相互作用によって症状が生じるという考え方もあります。そのため「育て方が原因」「しつけが悪い」ということではなく、様々な要因が影響し合って現在の症状があると理解できるとよいでしょう。
ADHD(注意欠如多動症)の子どもの行動を前向きに捉える
ADHDの子どもの行動や事象には、前向きに捉えられるところがたくさんあります。例えば、以下のようにネガティブに捉えがちなADHDの子どもの行動や事象への認識を置き換えて、関わる大人も子ども自身もポジティブな気持ちで向き合える場面を増やしていきましょう。
- 物事をやり遂げることができない:
→ 切り替えが早い - おしゃべりが過ぎる:
→ 積極的にコミュニケーションをとる - 質問が終わる前に答えてしまう:
→ すばやく反応できる
これらのように、その子の特性をポジティブな側面として捉え直すことで、自己肯定感を育み、本来持っている強みを伸ばすことにつながります。
特性を理解し、自分らしく生きる
ADHDは脳の機能障害によるものであり、その特性のために日常生活で困難を抱えることがあります。しかし、特性を理解し、適切な支援と接し方を学ぶことで、困りごとを減らし、その人が持つ力を最大限に引き出すことができます。
当カウンセリングルームでは、現役の看護師であり公認心理師である私が、メンタルクリニックや医師とは異なる立場から、ADHDの特性や困りごとを抱えるお子さま、そしてそのご家族に寄り添い、カウンセリングを通して、ADHDの特性を理解し、困りごとに対する考え方や行動パターンを見つめ直し、具体的な対処法や社会参加に必要なスキルを身につけるお手伝いをさせていただきます。お子さま一人ひとりの「個と環境へのアプローチ」を重視し、ご家族と共に、特性を強みとして活かし、自分らしく社会で活躍できるためのサポートをいたします。
一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。