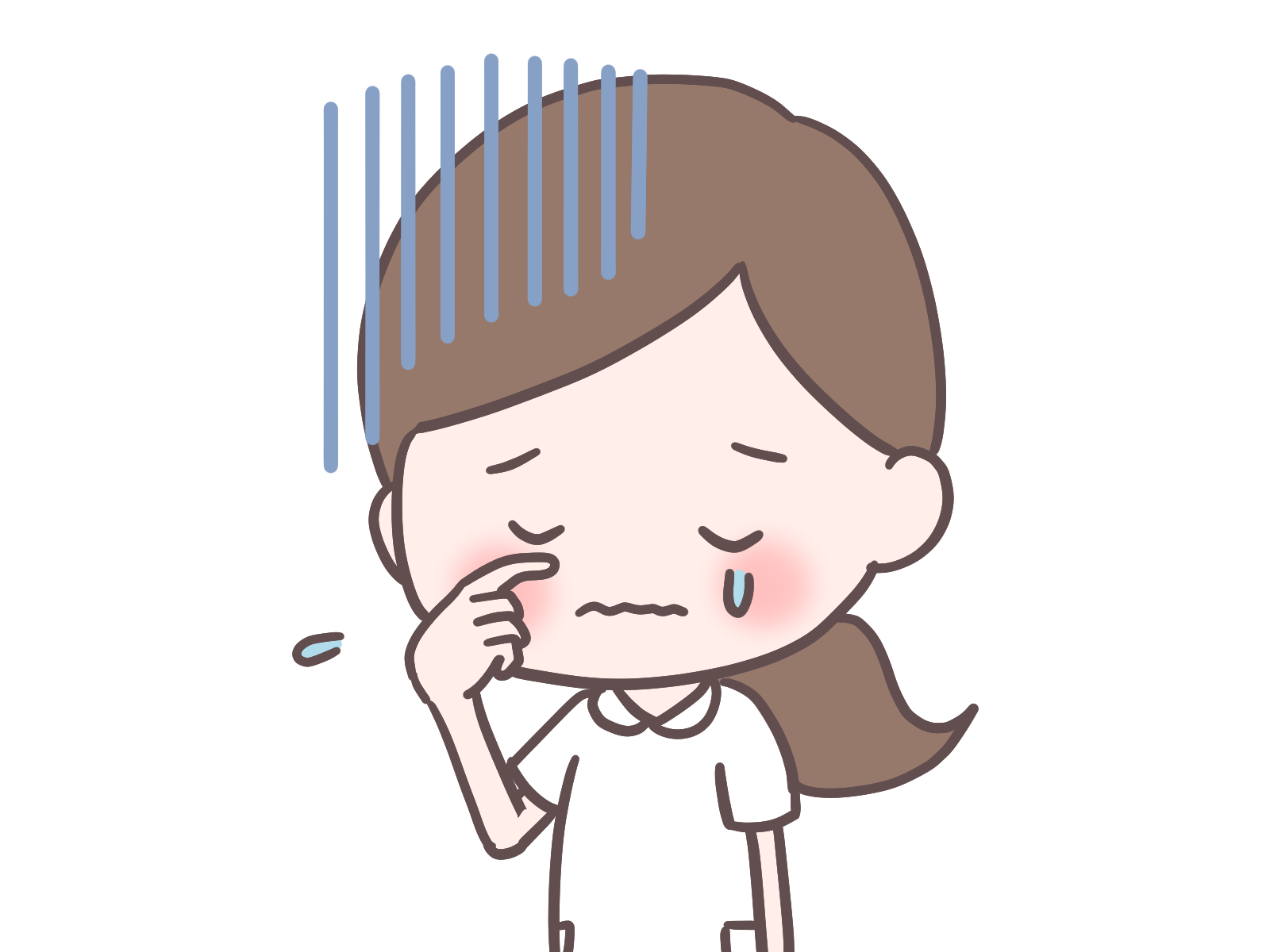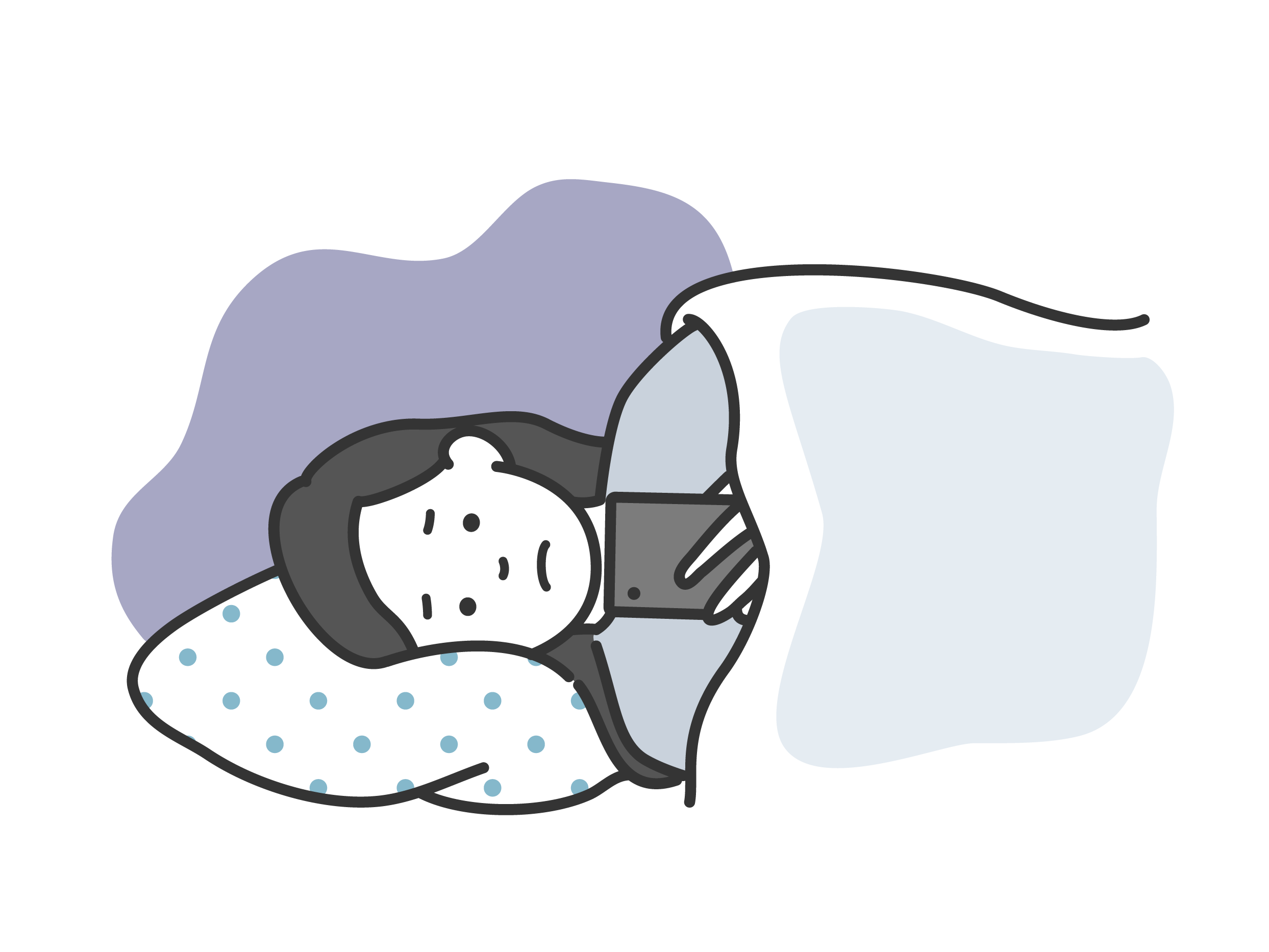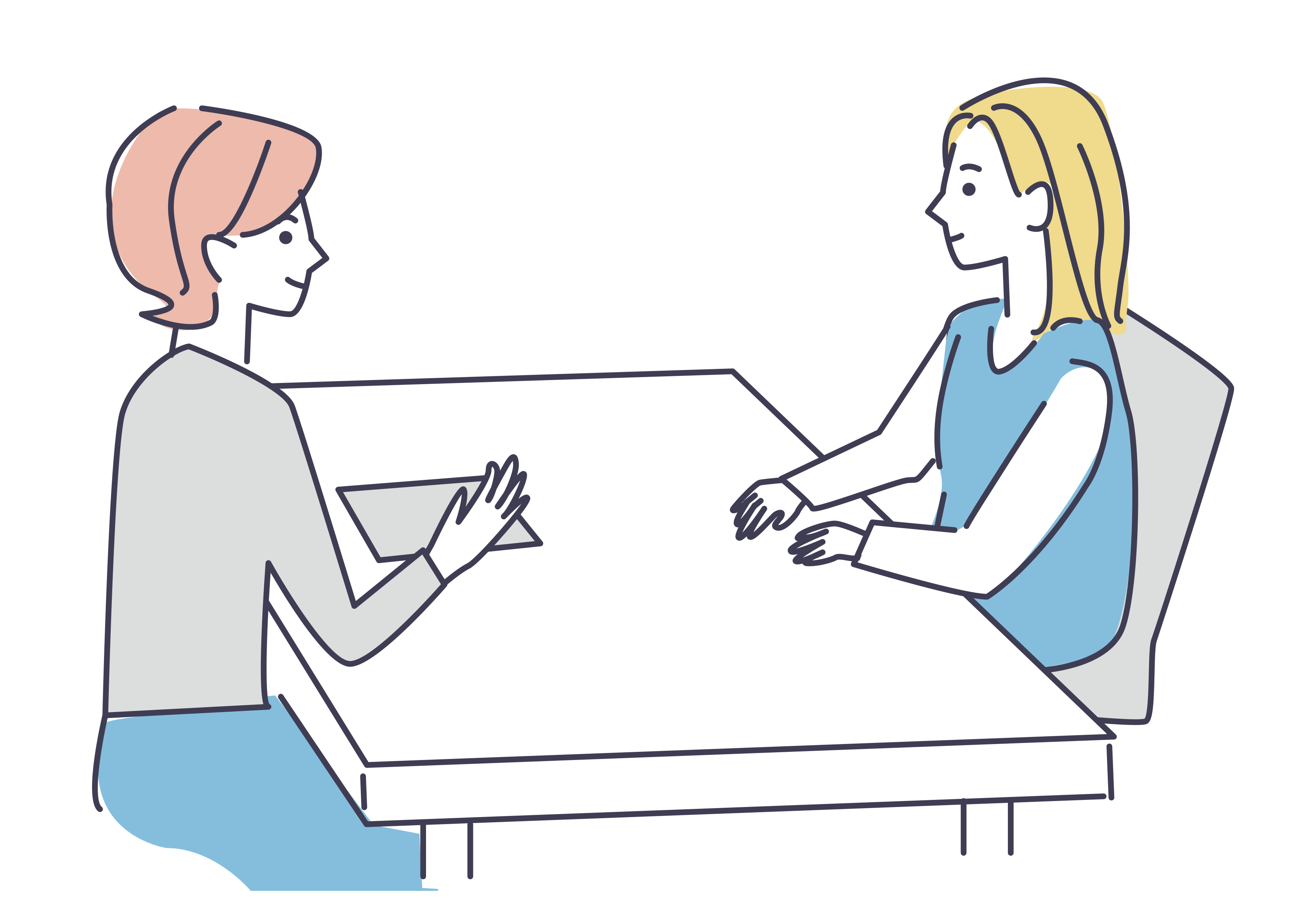睡眠障害の新しい常識:「薬より認知行動療法(CBT-I)」へ【10月10日:世界メンタルヘルスデーに考える】
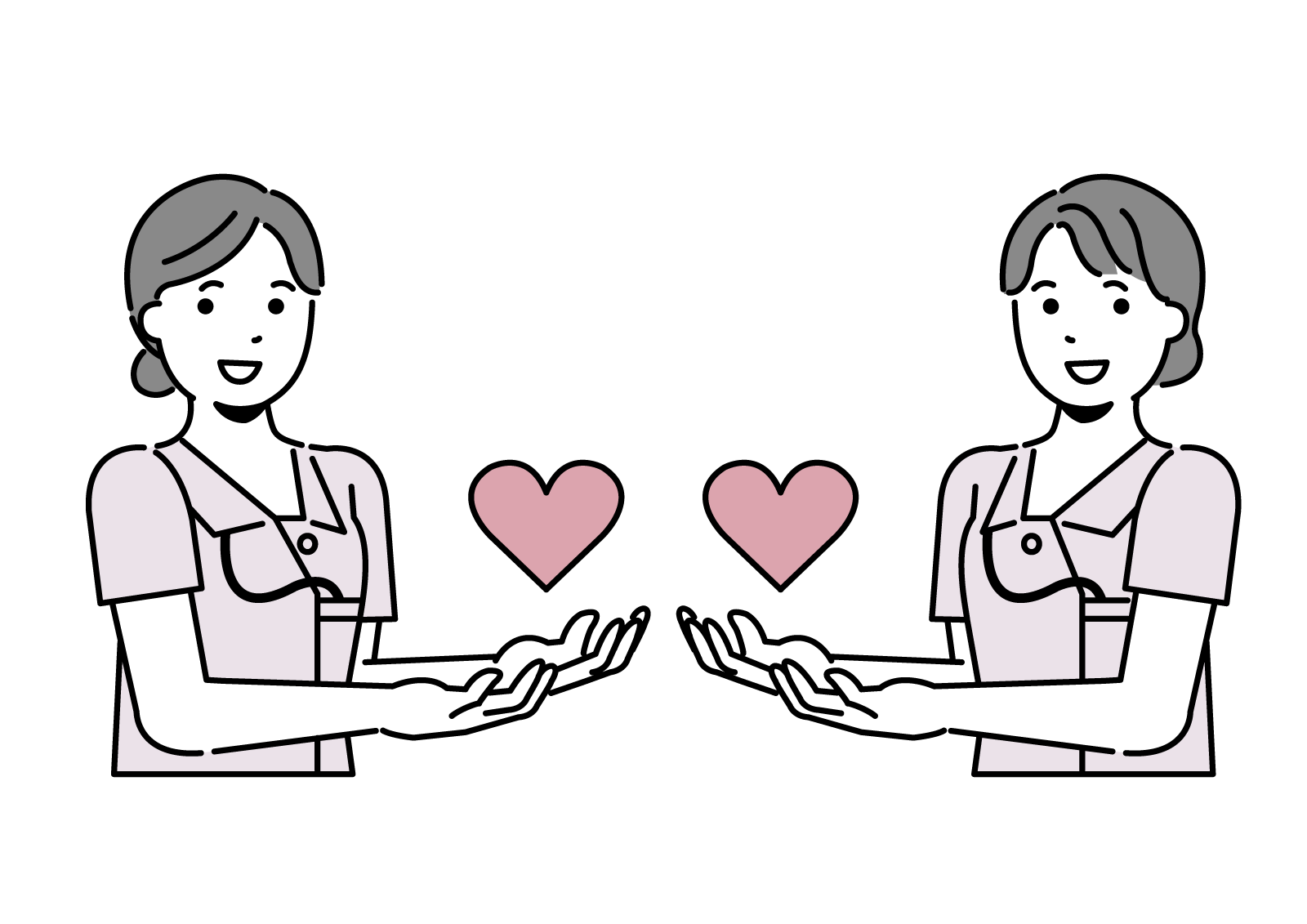
毎年10月10日は「世界メンタルヘルスデー」です。
現代社会において、心と体の健康は切っても切り離せないテーマであり、特に睡眠の質は、私たちのメンタルヘルスに深く関わっています。
日本国内では、生涯を通じて何らかの精神疾患になる方が5人に1人と推計されていますが、それに先立って睡眠障害に悩まされている方は3人に1人もいるという現状があります。
もしあなたが、寝付きの悪さ(入眠困難)、途中で何度も目が覚める(中途覚醒)、または極端な早朝に目が覚めてしまう(早朝覚醒)といった症状を、週に3日以上、3カ月以上続けているなら、それは治療が必要な「不眠症」かもしれません。これらの症状は、不眠症の4つのタイプ(入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠障害)の一部として挙げられます。
睡眠薬への依存リスクを超えて:世界の主流は「CBT-I」へ
睡眠障害の早期治療として、日本では今なお睡眠導入剤が処方されることが多いです。しかし、依存性の問題などから、世界の趨勢は認知行動療法(CBT-I)へとシフトしています。
認知行動療法(CBT)は、私たちが持つ「考え方(認知)」や「行動」のパターンを見直し、心のつらさを和らげる科学的根拠に基づいた心理療法です。そして、不眠症に特化したCBT-I(Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia)は、長期的な効果において薬物療法を上回る結果を示しています。
統合解析の結果、CBT-I単独での治療は、薬物療法単独と比較して、長期的(12〜48週)にぐっすり眠れるようになった、睡眠の質が改善されたと評価される寛解率が、およそ1.8倍と有意に高かったことが報告されています。さらに、治療からの脱落率も、CBT-I単独群が最も低かったというデータもあります。
このデータは、安易に睡眠薬に頼る治療法が時代遅れになりつつあることを示しています。
睡眠の質を高める具体的なステップ:「睡眠制限法(SRT)」
CBT-Iの中でも、特に有効性が確立されている手法として「睡眠制限法(SRT)」があります。
これは、ベッドで横になっている機会や時間(ベッドタイム)を意図的に制限することで、実際に眠っている時間の割合を、ベッドで過ごす時間の8割〜9割に調整する方法です。
例えば、実際の睡眠時間がベッドタイムの8割未満であれば、ベッドで横になる時間を15分短くし、逆に9割以上であればベッドタイムを15分長くします。この調整を繰り返すことで、最適なベッドタイムの中で「ぎゅっと凝縮された深い睡眠」を取れるようになることを目指します。
この治療を始めるには、まず睡眠日誌をつけて、平均睡眠時間やベッドタイム、そして睡眠割合を算出する必要があります。これは少々手間ですが、既存の睡眠日誌アプリを利用すると効率的です。
また、薬物療法を超えたCBT-Iを求める患者さん向けに、医師が不眠症患者に処方する医療用アプリ「サスメドMed CBT-i」(サスメド社)が製造承認を取得しており、現在、保険適用に向けて動いています。臨床での実装が期待されるでしょう。
お薬に頼る前に、まず「自分と向き合う時間」を
私たちは、夜なかなか眠れない状態が続くと、「眠らなければ」という過度なこだわりや恐怖心から、かえって不眠が悪化するという悪循環に陥りがちです。CBT-Iは、不眠の原因となっているこうした「眠り」に対する誤った考え方や、不適切な行動パターンを見つめ直し、修正していく根本的な改善を目指すアプローチです。
当カウンセリングルームでは、現役の看護師であり公認心理師である「さおちる」が、メンタルクリニックや医師とは異なる立場から、あなたの心の状態に寄り添います。
私たちは、心が疲れていると感じたとき、いきなりお薬に頼る前に、「カウンセリングで自分と向き合う時間」を持つことが、回復への大きな力になると確信しています。
不眠症(睡眠障害)の悩みは、日中の眠気や注意力の散漫、疲れなど、日常生活の質を大きく左右する重要な健康問題です。テクノロジーや心理療法など、様々なアプローチを使いつつ、健康的な睡眠を取り戻していきましょう。
一人で抱え込まず、質の良い睡眠を取り戻し、健やかな毎日を送るための具体的な対処法やストレス管理のスキルを身につけるために、いつでもお気軽にご相談ください。