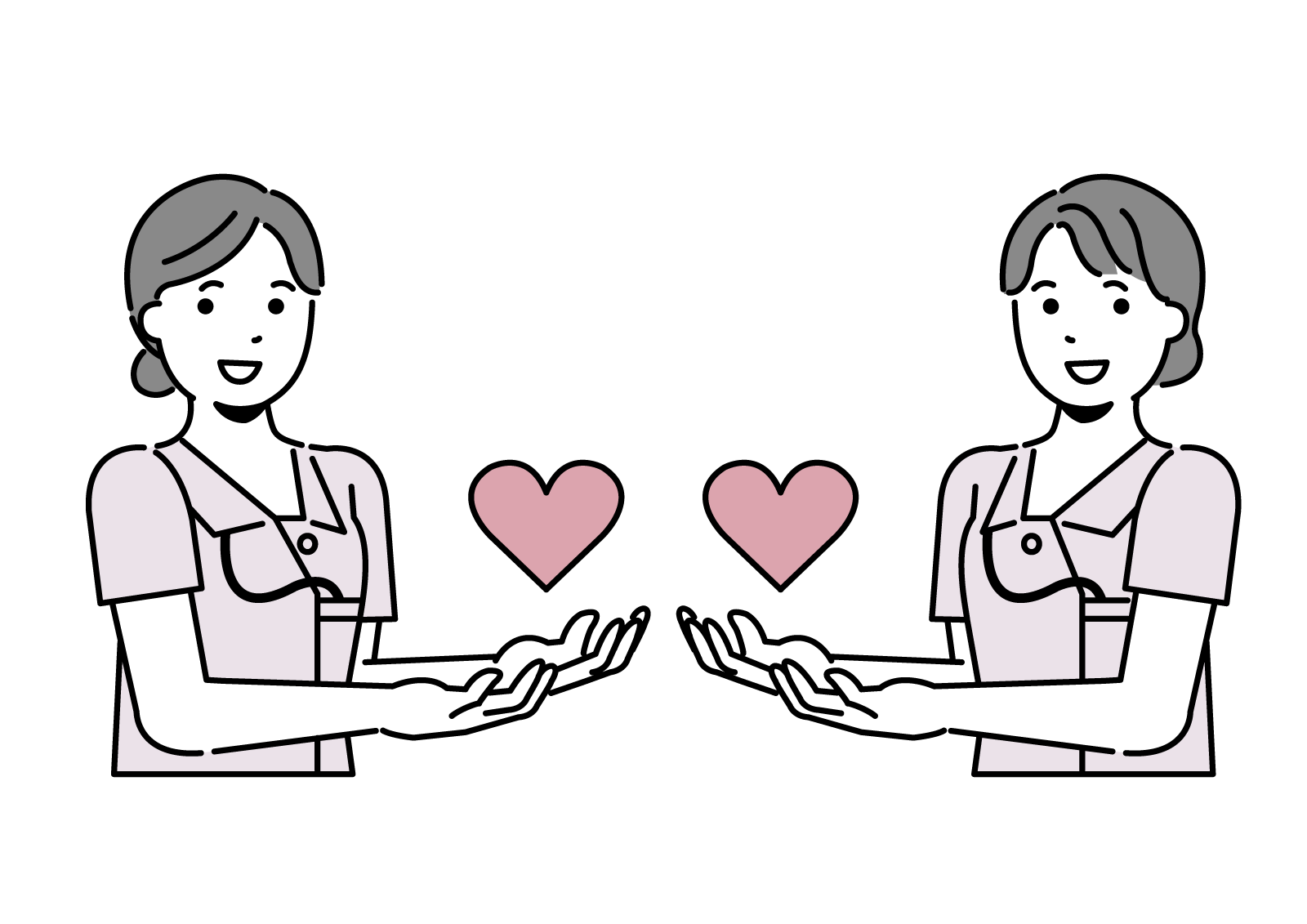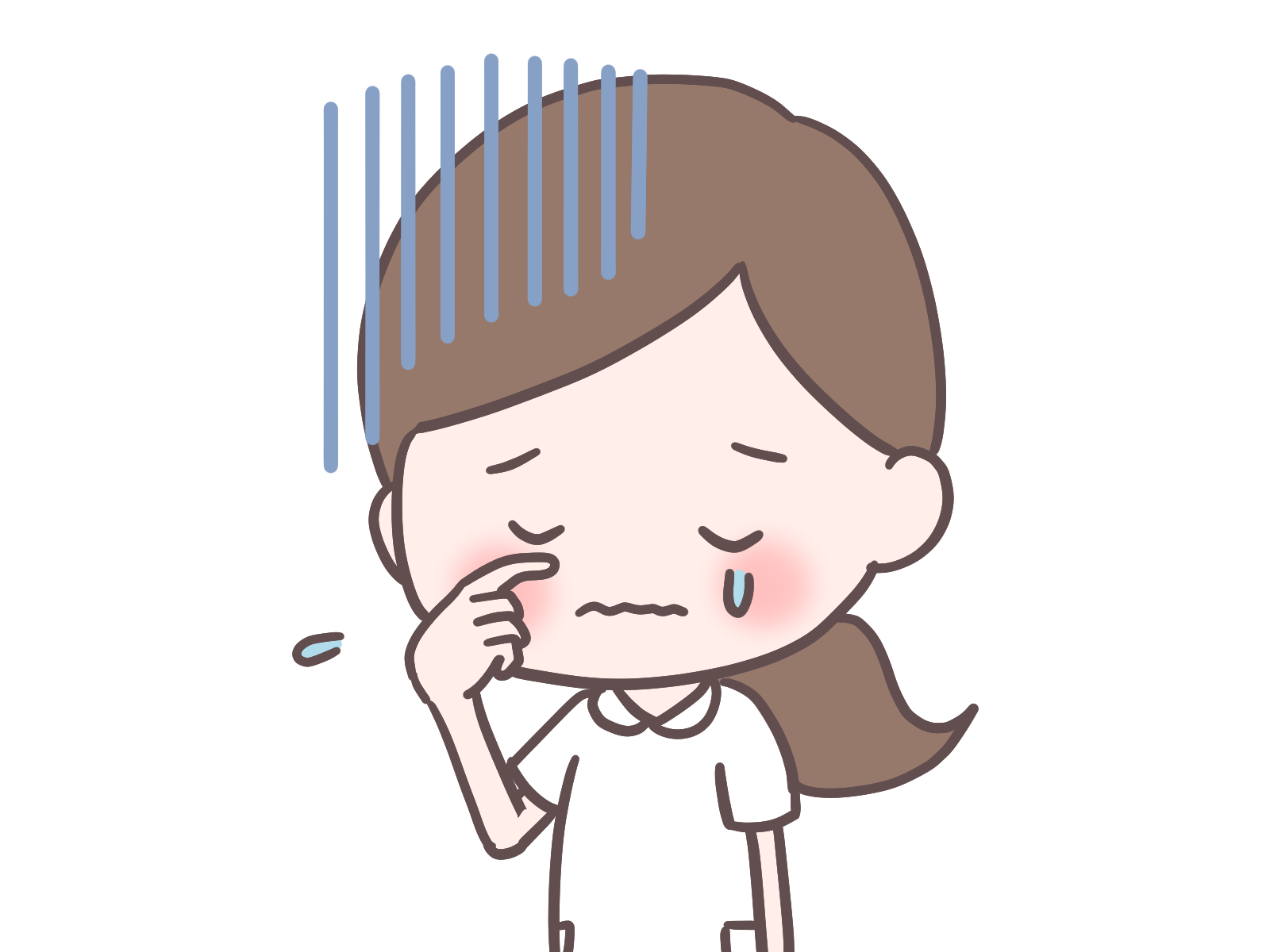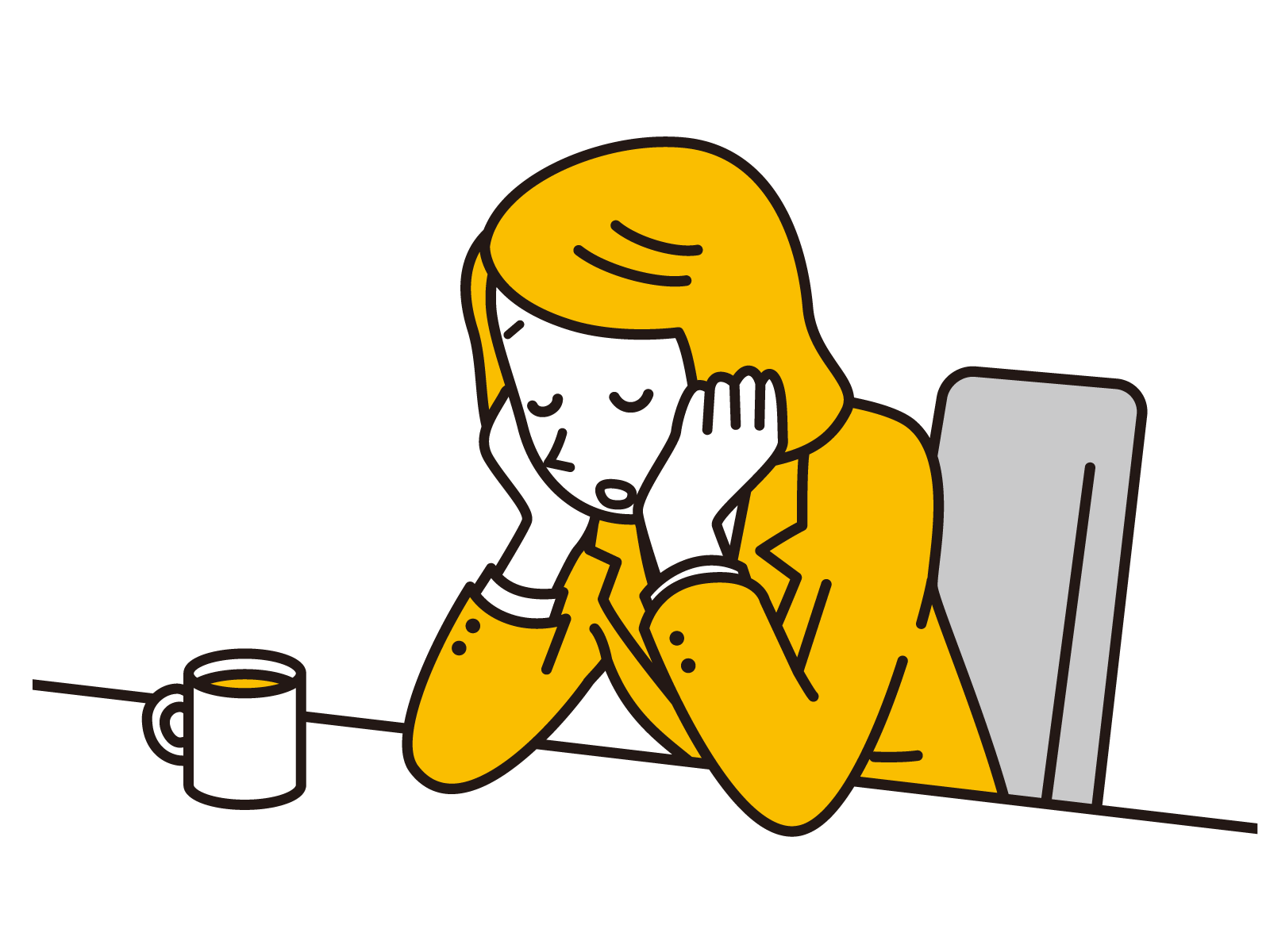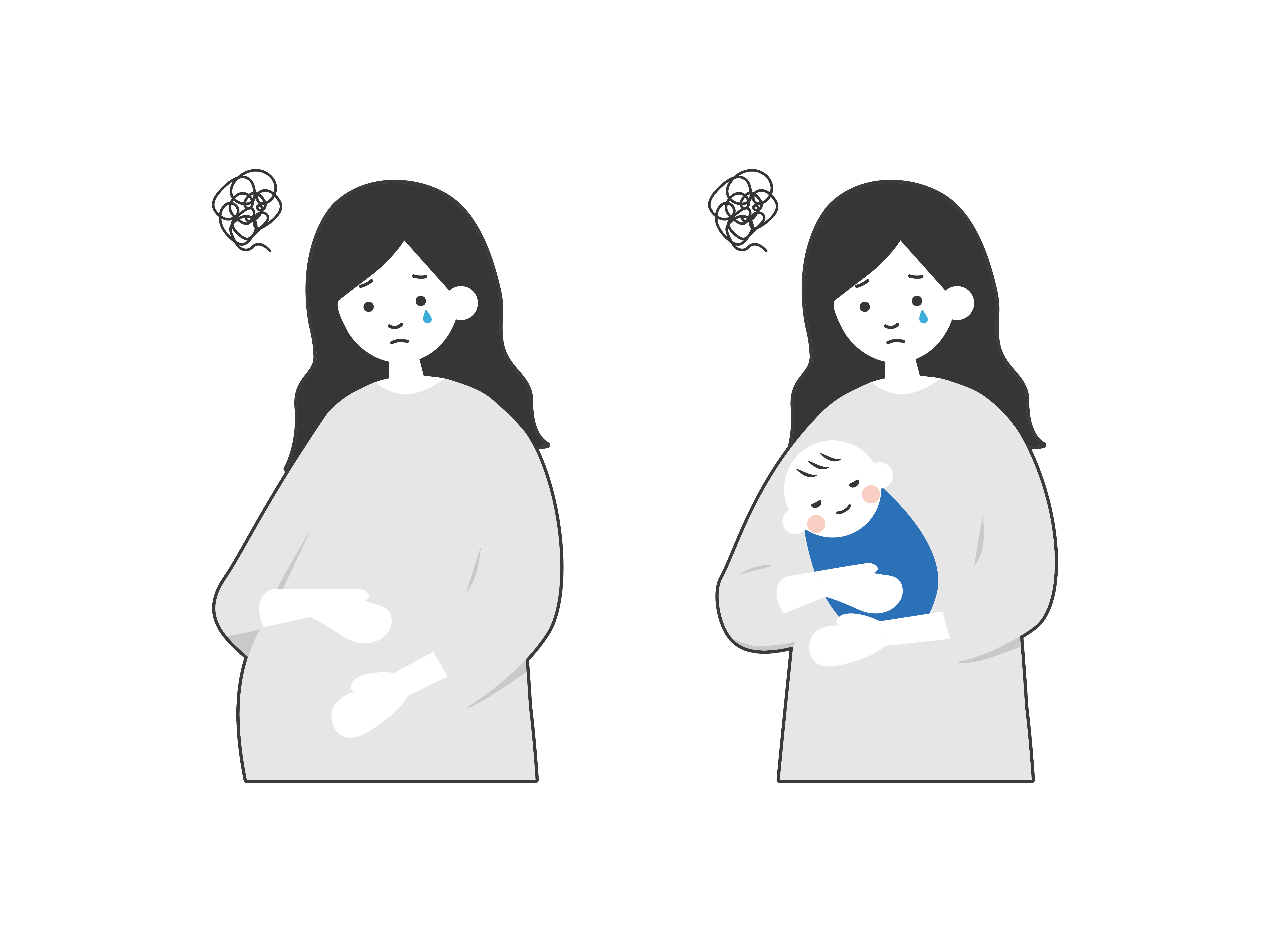摂食障害でお悩みの方へ:食事への苦しみから解放され、心身の健康を取り戻す

「食事の量や食べ方をコントロールできない…」「自分の体型がひどく太っているように見えてしまう…」「食べたものを意図的に吐いてしまう…」
もしあなたがこのような、食事に関連した行動の異常が続き、それが体重や体型のとらえ方などを中心に、心と体の両方に深刻な影響を及ぼしているとしたら、それは摂食障害かもしれません。
摂食障害は、若い女性を中心に増加している病気ですが、年齢や性別を問わず誰にでも起こりえます。この病気になると、からだとこころに様々な問題が生じて、毎日の生活に支障がみられるようになります。外見からは分かりにくいこともありますが、生命の危険を伴う身体合併症を引き起こすこともある、非常に深刻な病気です。しかし、この病気は治る病気です。
自分自身を責めず、一人で抱え込まずに、どうぞお気軽にご相談ください。
「摂食障害」とは?:食事への異常な行動と心身への影響
摂食障害は、食事の量や食べ方など、食事に関連した行動の異常が続き、体重や体型のとらえ方などを中心に、心と体の両方に影響が及ぶ病気をまとめて指します。日本で医療機関を受診している摂食障害患者は1年間に21〜24万人とされていますが、実際にはもっと多くの方が悩んでいると考えられます。
摂食障害には、主に「拒食症」と「過食症」の2つのタイプがあります。
1. 拒食症(神経性やせ症)
その名の通り、食べることを拒否してしまう病気です。
- 主な特徴:
- 体重が増えることへの強い不安や恐怖心があり、食べ物を受け付けなくなっていきます。
- BMI[体重(kg)÷(身長(m))²]が17.5以下と極端なやせとなっても、やせている状態を正常と考え、病気であることを認めないことが多いです。
- 治療には無関心であったり、治療への抵抗を示したりすることも多く見られます。
- 経過中に、沢山食べたいという欲求が抑えられなくなり、一時的に沢山食べて、その後に嘔吐して体重の増加を防ぐこともあります。
- 診断基準(抜粋):
- BMIが17.5以下。
- 体重減少は「太る食物」を避けることでなされる。
- 自分で誘発した嘔吐、下剤の使用、過度の運動、食欲減退剤あるいは利尿剤の使用が1つ以上ある。
- 太ることへの恐怖心がある。
- どんなに痩せていても、「自分は太っているに違いない」といった強迫的な考えがある。
拒食症の人は、どんなに痩せていても「自分は太っている」という誤った認識をしており、痩せ願望や肥満恐怖は強く、自らが痩せたいと望むため、自分が病気であるという自覚は得られにくいことが特徴です。本人は痩せた状態を維持することにより、ある種の達成感・万能感を感じ、現実の悩みから解放され、一時的に自信を持てるようになります。
しかし、自分の存在を肯定する理由が「痩せている自分」ですから、毎日が食べ物のこと、カロリーのことで頭が一杯になり、体重が減ることが「成功」であり、逆に体重が増えることが「失敗」であるように考えるようになります。こうして痩せを維持することで様々な精神的、身体的症状がみられるようになり、毎日の生活に支障が出てきます。
2. 過食症(神経性過食症)
抑えることが困難な「食べたい」という欲求が出現して、衝動的に沢山の食べ物を食べてしまう病気です。
- 主な特徴:
- 持続的に食べることに没頭し、食べたいという欲求が自分では抑えられません。
- 短時間に大量の食べ物を食べ尽くす「過食エピソード」があります。
- 過食での体重増加を防ぐために、嘔吐を繰り返したり、下剤を乱用したりすることもあります。
- 体重は標準〜肥満であることが多いです。
- 診断基準(抜粋):
- 過食(むちゃ食い)が繰り返されて、特定の時間帯に、他の人が食べる量よりも明らかに多い量を食べてしまい、食事量をコントロールすることができない感覚がある。
- 体重増加を防ぐために、嘔吐や下剤の利用、繰り返される絶食など、不適切な代償行動を繰り返している。
- 過食や代償行動が、ともに3ヶ月以上、平均週1回以上起きている。
- 自己評価が、体型と体重の影響を過度に受けている。
- 過食は、神経性拒食症の期間中にのみ起こるものではない。
過食症の人は、コントロール不能な過食行為に対して、挫折感や後悔を抱くようになります。自己嫌悪から抑うつ的となり、引きこもりや自傷行為がみられる人もいます。過食は本人にとって嫌なことを忘れさせてくれたり、考えなくてよいストレス解決方法となる一方で、同時に、無力感や自己嫌悪の念を強くするものでもあります。こうして悪循環が生じ、毎日の生活に支障が出てくるようになります。
摂食障害のサイン・症状:心と身体からのSOS
摂食障害の症状は多岐にわたり、患者さんによって現れ方が異なります。以下の症状のうち、いくつかでも当てはまる場合は、摂食障害の可能性があります。
食べることに関する症状
- 絶食する、食事の量やカロリーを極端に制限する、食べることが難しい、食欲がない。
- 大量に食べてしまい自分ではコントロールできない(むちゃ食い)。
- 食べたものを自分で嘔吐する。
- 下剤を決められた量以上に使ってしまう。
- 利尿剤ややせ薬を使ってしまう。
- 過剰に運動してしまう。
- (1型糖尿病に合併する場合)必要なインスリンを使わない。
体重や体形、食事への不安
- 体重や体形への強い不満がある。
- 周囲からはひどくやせていると言われるが、自分では、ちょうどいい、あるいは太っていると感じる。
- 強いやせ願望、あるいは体重が増えることへの強い恐怖がある。
- 食べ物のことや、カロリー、栄養のことが頭から離れない。
こころの症状
- 自尊心が低い。
- 精神的な苦痛がある。
- 抑うつ気分、不安、気分の変化が大きい。
- 性欲が低下している。
- 周りの人は心配するが、自分が病気とは思っていない(病識の欠如)。
- 周囲や社会から孤立している。
- 無気力、抑うつ状態になる。
- 自分に自信がない、もしくは過度に自信がある。
からだの症状
- 極端な体重の増加や、減少がある。
- 月経が止まり、不規則になる。
- 低体温、貧血、脱毛、うぶ毛が濃くなる、寒がり、皮膚の乾燥、むくみ、骨粗鬆症。
- 唾液腺の腫脹、齲歯(うし、虫歯のこと)、食道裂孔、胃けいれん、吐きダコ(嘔吐症状がある場合)。
- 味覚障害、聴覚過敏、けいれん。
- その他、疲れやすい、胃もたれ、便秘など。
摂食障害の原因:複雑に絡み合う要因
摂食障害の生物学的な原因はまだ明らかではありません。しかし、発症には心理的・社会的要因が複雑に絡み合っていると考えられています。
患者さんの多くは、生まれつき繊細な性格・体質であり、ある生活環境によって、自信が持てない・傷つきやすい・過度に周囲の評価を気にする、といった自己愛の強い人格が形成されていくことがあります。そこに、ダイエット・失恋・学業不振・人間関係でのトラブルなどの心理・社会的ストレスが加わることによって異常な食行動が出現することになります。
摂食障害の原因を特定することは大変困難なことであり、原因を探しても解決につながらないことが多く、かえって家族が傷つくだけで終わってしまうこともあります。原因を無理に探すのではなく、これからどうしていけばよいかを考えていくことが大切です。
病気という自覚の難しさ
拒食症の人は、自ら痩せたいと強く望んでいるため、どんなに痩せてもそれが病気だと認めることは難しいことが多いです。過食症の人は、自分が悪い・恥ずかしいといった思いから様々な問題を一人で抱え込んでしまう傾向があります。
摂食障害になる人は、小さい頃から周囲の願望や希望をくみ取って、自分の思いは抑え我慢し、周囲の願いを達成する形で生きてきていることが多いです。よく患者さんの親から「手のかからない子、良い子だった」と言われるのはこのためです。これまで自分を抑えて我慢してきたということは、それだけストレスを心の内にため込んでいるということになり、そのストレスが病気として形を変えて出現しているとも考えられます。
考え方を変えると、病気の発症は「これまでの生き方はもう無理で一人では頑張れない」という意味にも捉えることができます。この自分自身へのメッセージを素直に受け取り、一人で解決するのではなく、周囲に相談することが大切です。拒食・過食・嘔吐をしている自分を責めないで、そうせざるを得ない今の自分を認めてあげましょう。
摂食障害の治療と回復への支援:心身の回復と「自分らしさ」の再構築
摂食障害は回復することが可能な病気です。摂食障害は、体重や食事、栄養だけの問題ではありません。治療では、こころとからだの両面の問題を扱っていきます。それぞれの患者さんの症状や、症状の重さ、別の病気の有無や、背景の問題などを多面的に評価して、それに応じた治療をしていきます。
一般的に、治療に含まれる内容は以下の通りです。
- 治療に向けての信頼関係、協力関係の構築: 患者さんが安心して治療に取り組める関係を築きます。
- 摂食障害という病気の説明と動機づけ: 病気への理解を深め、回復への動機づけを行います。
- 症状の記録とモニター: 摂食・行動・身体・心理・社会面での症状を客観的に把握します。
- 身体管理と合併症の対処・治療: やせや栄養障害、嘔吐などによる身体の合併症があれば、それらに対処・治療します。
- 食事・栄養指導と再栄養療法: 正常な食習慣を指導し、体重を回復する必要がある場合には、医療管理下での再栄養療法を行います。
- 心理療法: 摂食障害に焦点化された認知行動療法など、専門的な心理療法が行われます。
- 他の精神疾患への対処・治療: 別の精神障害(発達障害、依存症など)や精神症状(不安、強迫、うつなど)をともなっている場合は、それらにも対処・治療します。
- 補助的な薬物療法: 必要に応じて、精神症状を和らげるために薬物療法を行うことがあります。
家族やケア提供者の摂食障害に対する理解と協力があると治療を進めやすくなりますので、家族への説明や支援も行われます。
治療は通常は外来で行いますが、著しい低体重や身体合併症がある場合、食事を全くとれない場合、精神的に不安定な場合などは入院で治療することがあります。
回復に向けて:時間と周囲の支え
一般的に摂食障害の治療は時間を要することが多く、数ヶ月で終わることもあれば年単位を要することもあります。症状は一進一退を繰り返して徐々に良くなっていきます。
回復の大切な要素として、周囲からの支え、自信を持てる活動や肯定的評価、そのままの自分を認めてくれる環境などがあり、これらを通して人は「自分らしさ」を作っていきます。回復への道は決して平坦ではありませんが、あせらず、あきらめず、ゆっくりと進みましょう。
摂食障害全国支援センターや摂食障害情報ポータルサイトなどからも、摂食障害に関する情報を得ることができます。
食事への苦しみから解放され、心身の健康を取り戻す
摂食障害は、心身に深刻な影響を及ぼし、日常生活を困難にする病気です。過食を止められないことへの無力感や自己嫌悪は、患者さんの心を深く傷つけます。しかし、この病気は回復することが可能です。
当カウンセリングルームでは、現役の看護師であり公認心理師である私が、メンタルクリニックや医師とは異なる立場から、あなたの心の状態に寄り添い、カウンセリングを通して、食事や体重、体型に対する「考え方の癖」や行動パターンを見つめ直し、それらを修正していくお手伝いをさせていただきます。主治医による薬物療法と並行して、ご自身で心の状態をコントロールし、正常な食習慣を取り戻し、心身ともに健やかな生活を送るためのサポートをいたします。
一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。