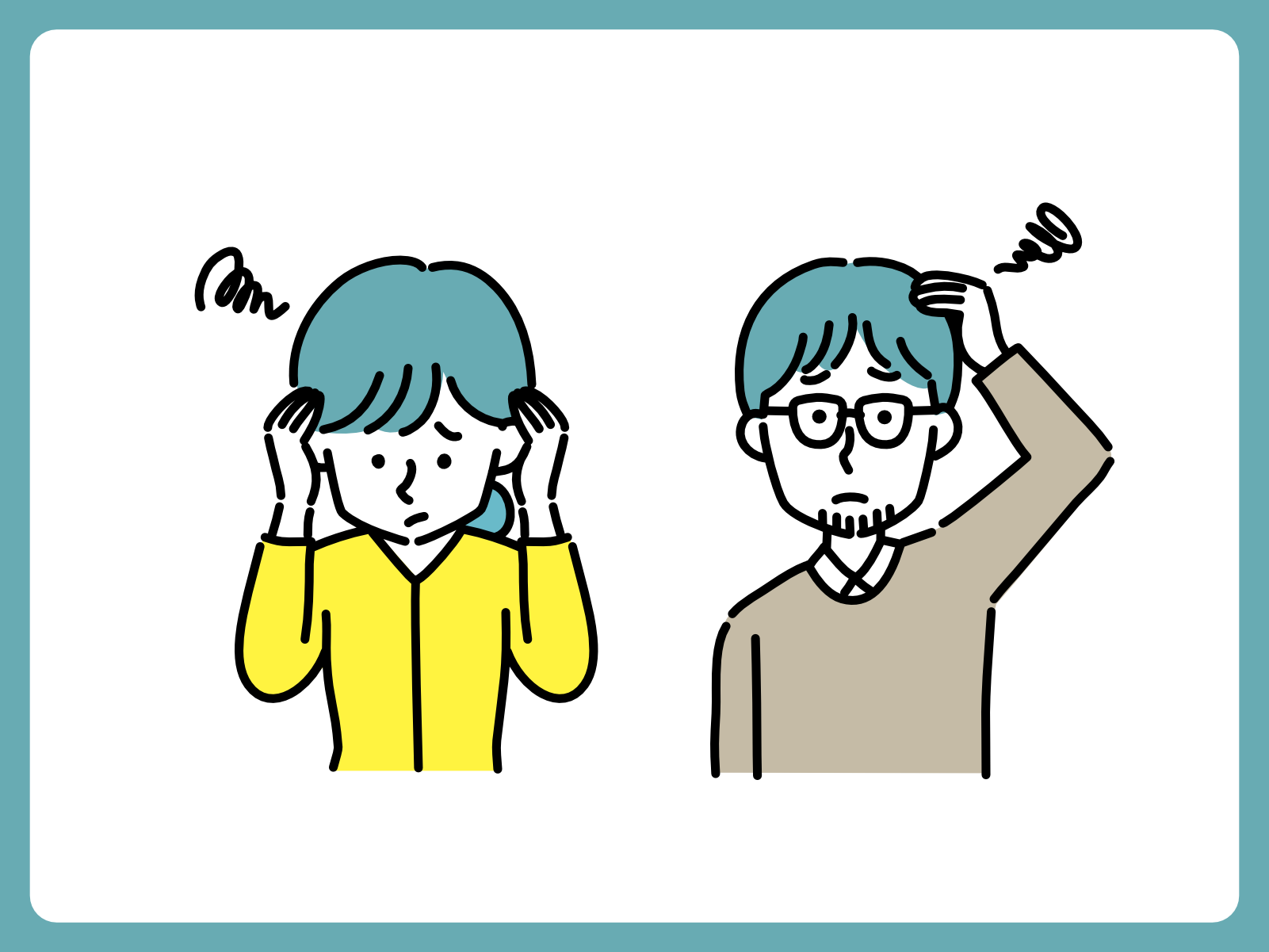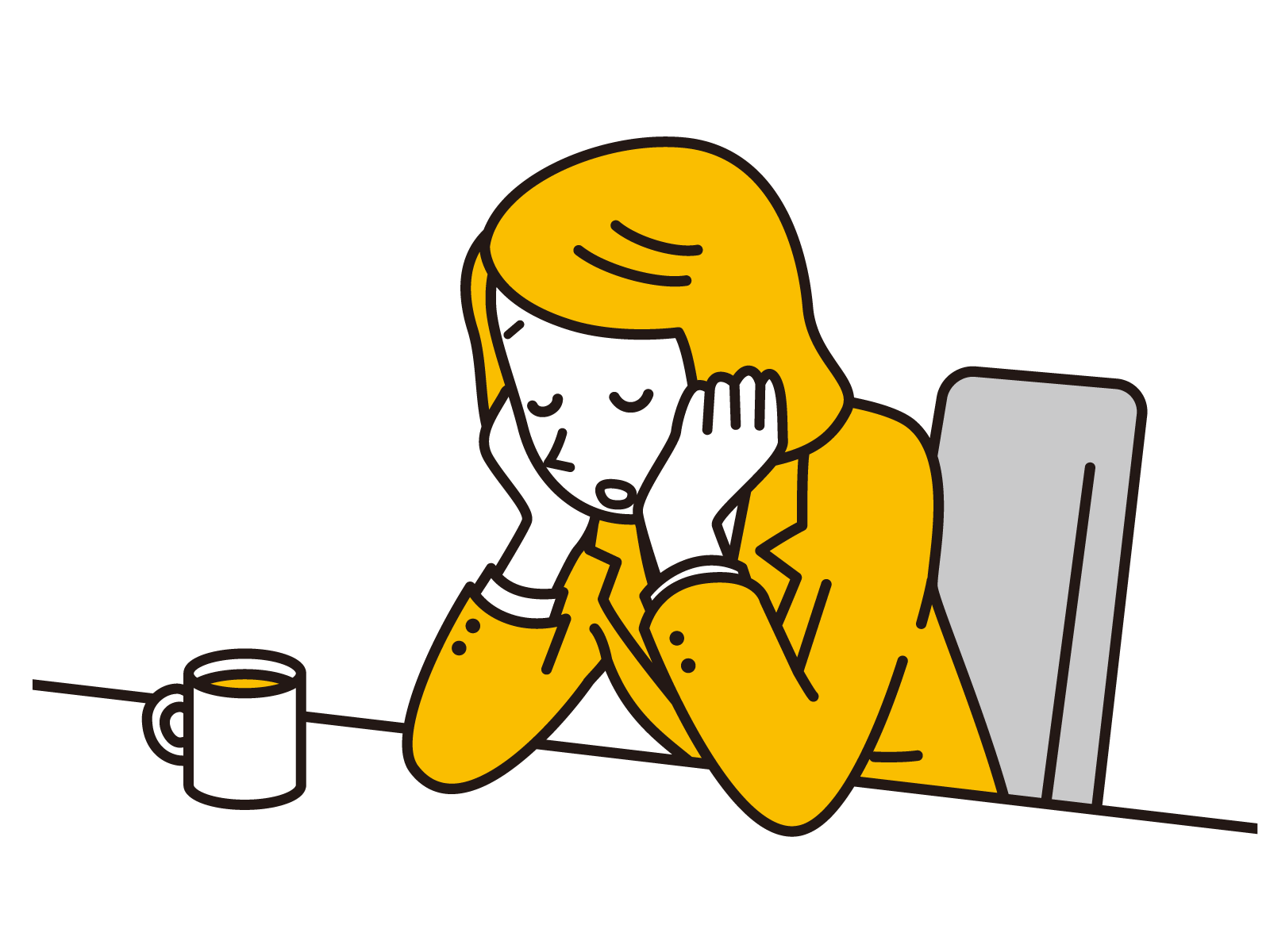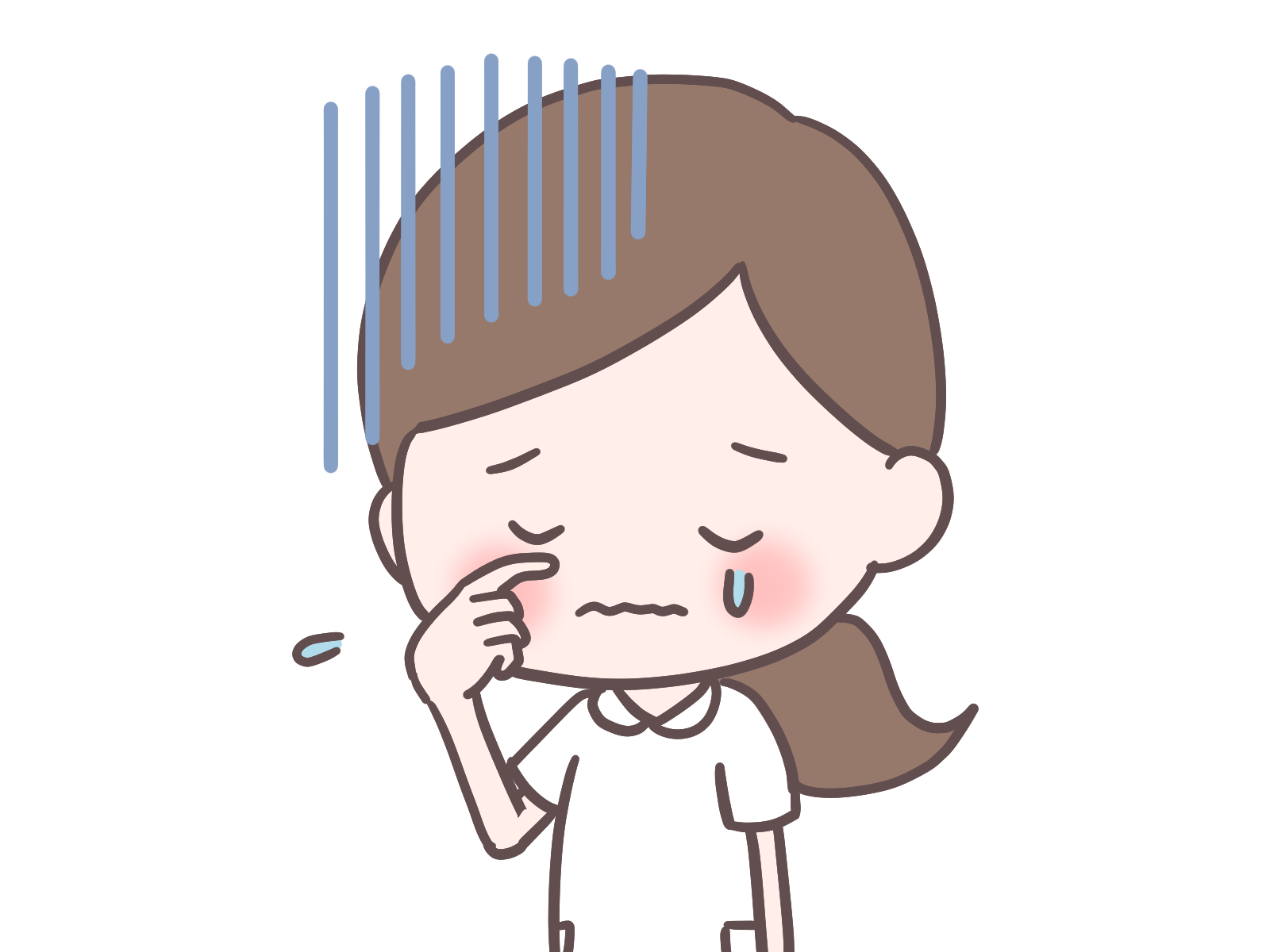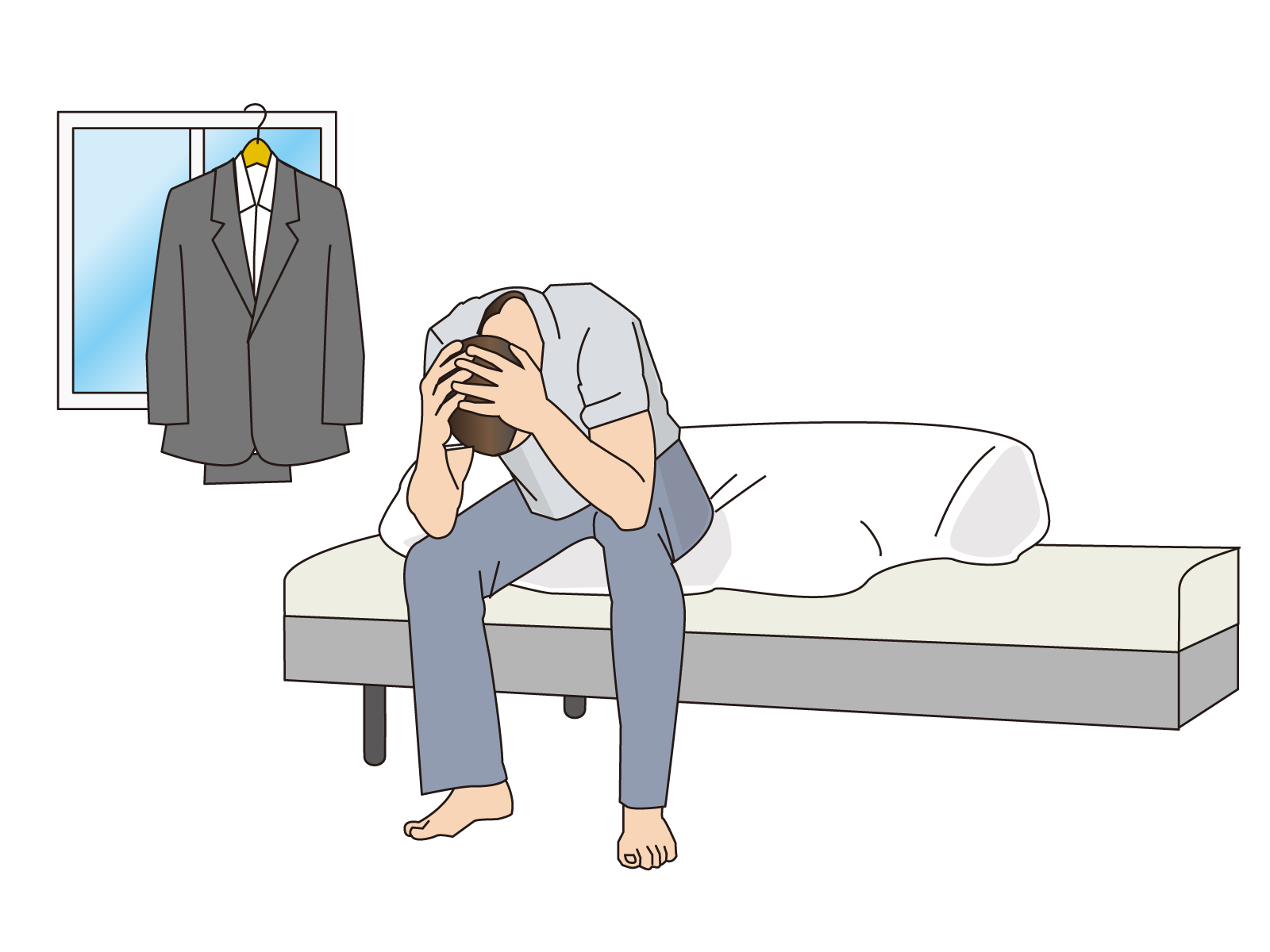ギャンブル等依存症でお悩みの方へ:コントロールできない衝動から解放され、自分らしい人生を取り戻す

「ギャンブルにのめり込んでしまい、やめられない…」「負けたお金をギャンブルで取り返そうとしてしまう…」「ギャンブルのことで嘘をついたり、借金をしたりしてしまう…」
もしあなたがこのような問題を抱えているとしたら、それはギャンブル等依存症かもしれません。
ギャンブル等依存症は、ギャンブル等にのめり込んでコントロールができなくなる精神疾患の一つです。これにより、日常生活や社会生活に支障が生じることがあります。例えば、うつ病を発症するなどの健康問題や、ギャンブル等を原因とする多重債務や貧困といった経済的問題に加えて、家庭内の不和などの家庭問題、虐待、自殺、犯罪などの社会的問題を生じることもあります。
ギャンブル等依存症は、適切な治療と支援により回復が十分に可能です。しかし、本人自身が「自分は病気ではない」などとして現状を正しく認知できない場合もあり、放置しておくと症状が悪化するばかりか、借金の問題なども深刻になっていくことが懸念されます。
この病気は、一時的な興奮や快感をもたらす一方で、その衝動がコントロールできなくなると、経済的な問題、人間関係の破綻、精神的な苦痛など、深刻な影響を及ぼします。しかし、適切な治療と支援を受けることで、コントロールできない衝動から解放され、自分らしい人生を取り戻すことが十分に可能です。一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。
「ギャンブル等依存症」とは?:ギャンブルの衝動がコントロールできない病気
ギャンブル等依存症とは、その人の人生に大きな損害が生じるにも関わらず、ギャンブルを続けたいという衝動が抑えられない病態をいいます。勝ちを追い求めて、最後には掛け金をたいてい失ってしまいますが、そのような行為を人に隠したり、貯金を使い果たしてしまったりします。借金が膨らんで、盗みや詐欺行為に手を染めてしまうこともあります。そして、最終的には生活が破綻して、深刻な事態に至ります。
いわゆるギャンブル依存症は、1970年代後半にWHO(世界保健機関)において「病的賭博」という名称で正式に病気として認められました。その後の研究によってこの病気への理解が進み、ギャンブルがやめられないメカニズムはアルコール依存症や薬物依存症と似ている点が多いことがわかってきました。このため、アルコール依存症等と同じ疾病分類(物質使用障害および行動嗜癖)に「ギャンブル障害」として位置づけられ、依存症として認められるようになりました。
ギャンブルとは、あるものを賭けてより価値のあるものを手に入れる行為をいいます。勝つか負けるかはほとんど偶然に支配されています。日本では、競馬、競輪、競艇、オートレースなどの公営ギャンブルや、宝くじ、スポーツくじ、パチンコ、スロットの遊技などがギャンブルに当てはまるでしょう。
全くギャンブルをしない人もいれば、楽しみのためにギャンブルを行う人もいます。たいていの人はこのカテゴリーに当てはまりますが、中には、ギャンブルによって、金銭的な問題だけでなく、個人の生活に影響を及ぼす場合があります。それがギャンブル依存といわれるものです。
ギャンブル等依存症の具体的な症状:自己と社会への深刻な影響
ギャンブル等依存症の具体的な症状としては、以下のようなものが挙げられます。
- ギャンブルへののめり込み:
- ギャンブルにのめり込む。
- 興奮を求めて掛金が増えていく。
- ギャンブルを減らそう、やめようとしてもうまくいかない。
- ギャンブルをしないと落ち着かない。
- 負けたお金をギャンブルで取り返そうとする。
- 行動の変化:
- ギャンブルのことで嘘をついたり、借金したりする。
- ギャンブルをする時間を確保するために、家庭や仕事の約束を破る。
- 深刻な問題への発展:
結果として、人間関係のトラブル、破産を含む金銭問題、法律問題や違法行為を働いたことによる懲役、仕事能率の低下や失業、健康問題、希死念慮や自殺などの深刻な問題に至ることがあります。
ギャンブル依存のメカニズム:脳の報酬系の機能異常
ギャンブルをなかなか止められない、しばらく止めていても久しぶりにすると止められなくなる。これには、脳内のいわゆる報酬系などの機能異常が原因と考えられています。
脳内には、「脳内報酬系」と呼ばれる部位があります。我々が感じる、気持ちよさ、ワクワク感、多幸感などは、この部位が働いて生まれます。ギャンブルも、やり始めの頃に大儲けした時など、この部位が強く反応して、ドーパミンという快楽物質が大量に作られ、放出されます。
しかし、ギャンブルをやり続けて依存状態になるにつれて、この部位は快楽に鈍感になり、ギャンブルの勝ちにもだんだん反応しなくなります。こうなると、ギャンブルだけでなく、おいしい食事、お酒、セックスなど本来は楽しいはずのものも、楽しいと感じられなくなっていきます。
一方、依存状態になると、自分がしているギャンブルを連想させる何か(例えば、パチンコの台)を見たり、聞いたりすると、その時だけ脳の一部が強く反応し、「ギャンブルをしたい」という強い欲求に襲われます。
この欲求を満たすためにギャンブルをしても、ドーパミンが放出されないために、この欲求は十分に満たされません。その結果、益々ギャンブルがエスカレートしていくわけです。
このような脳の機能は元の健康な状態に戻るのでしょうか。研究によると、ギャンブルを断つと、年余の時間はかかるものの、元の状態にゆっくりと戻ってゆくとのことです。しかし、ギャンブルを続けると、益々悪くなっていきます。
ギャンブル依存になりやすい人:様々な要因が影響
ギャンブル依存の原因について、まだはっきりとしたことはわかっていませんが、生物学的要因、遺伝的要因、環境要因が組み合わされて発症している可能性があります。
また、薬物やアルコールと同じように、前述のような脳内の報酬系という神経回路が亢進しているため、という説もあります。
これまでの研究等から、発症に影響を与えうる要因として、以下のようなものがあげられています。
- 年齢、性別: 若い人、男性がリスクが高いとされています。
- 性格傾向: ストレスへの対処がうまくない人。
- 環境要因: ギャンブルが身近にある環境。パチンコやスロットのような電子ゲーム機の場合は、機械そのものに依存させる要因があります。
- 家族や友人の影響: ギャンブルをする家族や友人がいる。
- 精神疾患: 後述する併存疾患がある場合。
- パーキンソン病の治療薬: 特定の薬物がギャンブル依存のリスクを高めることがあります。
ギャンブル依存症の診断基準:WHOとDSM-5
ギャンブル依存の診断基準(DSM-5)
アメリカ精神医学会の精神疾患の診断基準である「精神疾患の分類と診断の手引き」(DSM-5) において、【ギャンブル障害】として記述されています。
(具体的な診断基準は医療機関で専門医が評価します。)
どのくらいの患者数がいるのか
- 海外の研究: 一般人口におけるギャンブル依存の有病率は、0.4〜2.0%の幅で推計されています。また、ギャンブル依存まで至らないが、ギャンブルに問題のある人まで含めると、さらに1.3〜2.3%増えると推計されています。
- 日本における調査: ギャンブル依存の有病率に関する調査はほとんどありませんが、厚生労働科学研究によると、ギャンブル依存が疑われる人の数は、平成25年度で4.8%と推計されています。今後、日本のギャンブル依存の問題を考えるうえで、さらなる実態調査が必要と考えられます。
併存疾患:ギャンブル依存症と関連する他の心の病
ある病気が他の病気と一緒にみられる場合を併存疾患と言います。ギャンブル依存には精神疾患の合併が多く、特に以下のような疾患が多いとされています。
- ニコチン依存を含む物質使用障害
- アルコール乱用や依存症といったアルコールの問題
- うつ病などの気分障害(躁うつ病を含む)
- パニック障害などの不安障害
合併する頻度は調査によっても異なりますが、11件の調査をまとめて解析した論文によると、ニコチン依存が60%、アルコールや薬物の問題が58%、躁うつ病を含む気分障害が48%、不安障害が37%などとなっています。
一方、アルコールや薬物に問題のある人にもギャンブル依存が多いとされていて、31件の論文をまとめて解析した調査によると、ギャンブルに何らかの問題がある人の割合は23%、ギャンブル依存と考えられる人の割合は14%と報告されています。
また、アルコールや薬物の問題のないギャンブル依存の人は、アルコールや薬物に問題を抱えたギャンブル依存の人より治療成績が良いとされており、ギャンブルの問題とアルコールや薬物の問題が相互に影響し合っていることが指摘されています。
ギャンブルの問題がある人とない人を対象に精神疾患について調査した研究によりますと、ギャンブル依存の4人中3人はギャンブル以外の精神科の病気が先にあり、その後にギャンブルの問題が発生したとされていますが、約3万3千人を3年間追跡した調査によりますとアルコール依存、気分障害、不安障害、心的外傷後ストレス障害 (PTSD) といった精神科の病気が起こりやすくなることが報告されており、アルコールや薬物依存、うつ病といった精神科の病気がギャンブル依存の原因になったり、逆にギャンブル依存がうつ病やアルコールの問題の原因になったりといった形で相互に影響していると考えられます。
このような併存症の問題はギャンブル依存における希死念慮や自殺といった重大な問題と関連することが指摘されていますので、ギャンブルの問題を抱えた人にこれらの精神科の病気が見られないか注意する必要があり、併存症が見られる場合には適切な治療が必要です。
ギャンブル等依存症の治療と回復への支援:新たな生活の構築
ギャンブル等依存症は、決して本人の意思が弱いから起こるものではありません。脳のメカニズムが関与する病気であり、適切な治療と支援を受けることで回復が可能です。
1. 認知行動療法:思考の偏りを修正し、対処法を身につける
ギャンブル等依存症の治療では、ギャンブルに対する偏った考え方を見直し、金銭管理をはじめとした日常生活を変えたりすることでギャンブルをしたい気持ちを低減させたり、効果的な対処法を身につける認知行動療法と呼ばれる治療プログラムが有効です。
認知行動療法では、以下の点に焦点を当てて支援します。
- 思考の修正: ギャンブルに対する誤った確信や偏った記憶、迷信的な考え方を見つめ直し、より現実的で建設的な思考パターンを習得します。
- 行動変容: ギャンブルの衝動に打ち勝つための具体的な行動戦略を学びます。例えば、ギャンブルにアクセスしにくい環境を整える、別の活動で衝動を回避・対処する、などです。
- 金銭管理: ギャンブルによる経済的損失を防ぐため、適切な金銭管理の方法を学び、実践します。
2. 自助グループへの参加:仲間とのつながりが回復を支える
ギャンブラーズ・アノニマス(GA)など、ギャンブル依存症の人たちが相互に支えあう自助グループが全国にあります。GAミーティングに参加することは、病気からの回復の大きな助けになります。
- 経験の共有: 同じ悩みを抱える仲間と経験を共有することで、孤独感を軽減し、共感と理解を得られます。
- 相互支援: 仲間からのサポートや助言を受けることで、回復へのモチベーションを維持し、困難を乗り越える力を得られます。
- 継続的な回復: 定期的なミーティングへの参加は、回復への道を継続的に歩む上で非常に重要です。
3. 医療機関との連携
ギャンブル等依存症は、アルコール依存症や薬物依存症と同様に、専門医の診断と治療が必要です。精神科や心療内科では、薬物療法を併用したり、ギャンブル等依存症に特化した治療プログラムを提供したりすることもあります。
ギャンブル等依存症に関する相談窓口:一人で抱え込まずに相談を
ギャンブル等依存症は、本人自身が「自分は病気ではない」などとして現状を正しく認知できない場合もあり、放置しておくと症状が悪化するばかりか、借金の問題なども深刻になっていくことが懸念されます。そこで、ギャンブル等依存症に関する注意事項や、対処に困った場合の相談窓口をお知らせします。相談の内容に応じ、これらの窓口をご利用ください。
借金問題を相談する窓口
ギャンブル等依存症は、借金の問題を抱えることが非常に多いため、これらの問題に特化した相談窓口も重要です。
- 消費者ホットライン
- 多重債務者向け相談窓口
- 法テラス・サポートダイヤル(日本司法支援センター)
- 公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会
- 日本貸金業協会
- 全国銀行協会カウンセリングサービス
- 弁護士会(各地の弁護士会相談窓口)
- 各地の司法書士会一覧
保健・医療関係の機関
ギャンブル等依存症の治療や回復に向けた支援について相談できます。
- 都道府県及び政令指定都市の精神保健福祉センター
- 保健所
- 専門の医療機関
ギャンブル等依存症の支援団体
- 公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会
- NPO法人全国ギャンブル依存症家族の会
自助グループ
- GA日本インフォメーションセンター(当事者向け)
- 一般社団法人ギャマノン日本サービスオフィス(家族・友人向け)
競技施行者・事業者における対応窓口
のめり込みに不安がある方への対応として、各競技施行者・事業者も相談窓口を設けています。
- 日本中央競馬会インフォメーションデスク
- 各地方競馬場における窓口
- 競輪に係る公益財団法人JKAお客様相談コーナー
- オートレースに係る公益財団法人JKAお客様相談コーナー
- モーターボート競走(家族申告によるアクセス制限、本人申告による利用停止など)
- ぱちんこ(自己申告・家族申告プログラム)
- 一般財団法人ギャンブル依存症予防回復支援センターサポートコール
- 認定特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク
ギャンブル等依存症からの回復に向けて:ご本人とご家族へ
本人にとって大切なこと
- 小さな目標を設定しながら、ギャンブル等をしない生活を続けるよう工夫し、ギャンブル等依存症からの「回復」、そして「再発防止」へとつなげていきましょう(まずは今日一日やめてみましょう)。
- 専門の医療機関を受診するなど、関係機関に相談してみましょう。
- 同じ悩みを抱える人たちが相互に支えあう自助グループに参加してみましょう。
家族にとって大切なこと
ギャンブル等依存症は、嘘をついて家族との関係を悪化させる、ギャンブル等に必要な資金を得るために家族の生活費を使い込み、借金を重ねる場合も多く、本人のみならず、その家族の生活に多大な支障を生じさせる精神疾患であることから、ギャンブル等へののめり込みによる被害から家族を守ることもまた社会的な要請ということができます。
- ギャンブル等をしている方に、家族の行事を顧みなくなった、家庭内の金銭管理に関して暴言を吐くようになった等の変化が見られる場合、ギャンブル等へのめり込み始めている可能性を考慮しましょう。家族だけで問題を抱え込まず、家族向けの自助グループに参加するなど、ギャンブル等依存症が疑われる方に振り回されずに健康的な思考を保つことが何よりも重要です。
- 自助グループのメンバーなど、類似の経験を持つ人たちの知見などをいかし、本人が回復に向けて自助グループに参加することや、借金の問題に向き合うことについて、促していくようにしましょう。
- ギャンブル等依存症が病気であることを理解し、本人の健康的な思考を助けるようにしましょう。
- 借金の肩代わりは、本人の回復の機会を奪ってしまいますので、家族が借金の問題に直接関わることのないようにしましょう。
- 専門の医療機関、精神保健福祉センター、保健所にギャンブル等依存症の治療や回復に向けた支援について相談してみましょう。
- 消費生活センター、日本司法支援センター(法テラス)など借金の問題に関する窓口に、借金の問題に家族はどう対応すべきか相談してみましょう。
コントロールできない衝動から解放され、自分らしい人生を取り戻す
ギャンブル等依存症は、脳のメカニズムが関与する病気であり、その衝動がコントロールできなくなることで、ご本人だけでなく周囲の人々にも深刻な影響を及ぼします。しかし、この病気は決して「治らない」ものではありません。適切な治療と継続的なサポートがあれば、ギャンブルの支配から解放され、より健康的で充実した自分らしい人生を取り戻すことが可能です。
当カウンセリングルームでは、現役の看護師であり公認心理師である私が、ギャンブル等依存症の問題に悩むご本人やご家族に寄り添い、認知行動療法によるカウンセリングを通して、ギャンブルへの衝動の背景にある思考の偏りや感情、ストレスへの対処法を見つめ直し、ギャンブルに頼らない生活を送るための具体的なスキルや行動計画を立てるお手伝いをさせていただきます。必要に応じて、専門医による医療的治療や自助グループ、公的機関との連携をサポートし、ご自身がギャンブルの問題から抜け出し、より健康的で充実した自分らしい人生を送るためのサポートをいたします。
一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。